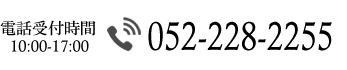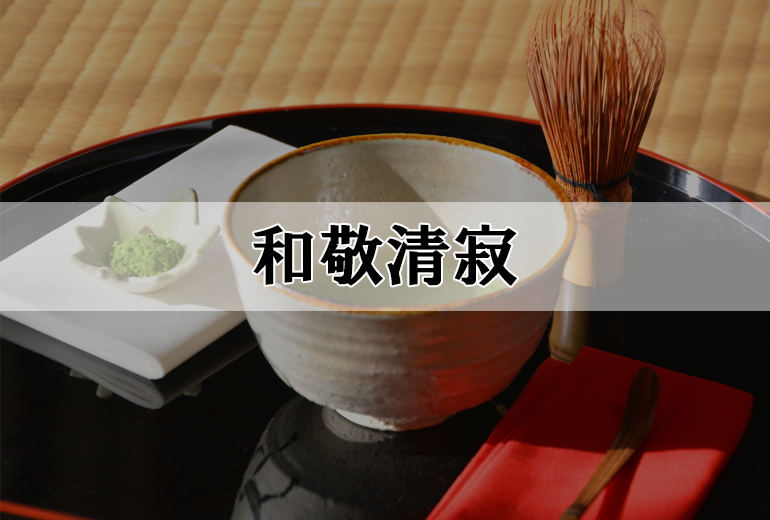和敬清寂
米国大統領の初来日の様子を世界が報道する中、5月23日夜、その訪問を歓迎し、総理夫人が抹茶を振る舞う様子が、写真とともに報道された。
2013年に「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録され、フランスでの日本文化に対する関心の高まりなどもあり、茶道の本家である日本より、最近は海外にて関心が非常に高いという。抹茶、道具とともに、その禅に通じる精神性は、座禅とともに世界の人々に広く受け入れられている。茶の湯の世界において、「和敬清寂」の言葉は、「茶の湯」の根本に流れる精神性を表す言葉として広く語られている。その言葉には、「誰とでも仲良く、すべてにおいて調和を大事にし、お互いを尊重し合い、何事も心から清らかであること、それによって穏やかでどんなときにも動じない心にいたる」という意味を込めているといわれる。
茶の湯の精神とは
騒然とした世情、混迷を深める現代社会のなかで、心の安寧と平常心を保つことがいかに大切かを思い知らされる昨今である。
茶の湯、その基本の精神は、一服の茶のために、隅々まで心配りのされたもてなしの作法を含め、迎え入れる客を思いやる事前の心配りに尽きるだろう。何日も前から準備し、茶室を掃き清め、茶道具を調え、茶菓を選び、花を生け、墨書を掲げ、亭主と客が「一座建立」の精神で、一服の茶のひと時に心を通わせ、世事を忘れ、美味しい抹茶、茶菓、選ばれた道具、掛け軸などを通して、充実感の高い時間をともに分かち合う喜びに尽きるだろう。古来より濃密な精神性を含んだ生活芸術とでも言うべき「茶の湯」の心の持ち様は、「和敬清寂」の四文字の普遍的な精神性に昇華される。
一人前と言われるまで、長く地道な稽古、実体験を通して身に着けていくのが茶道の修業であり、その神髄は相伝により、一対一で教授されるべきものとされ、禅宗の思想を背景に、子弟関係ともいえる厳しい修行の日々を経て、理屈でなく自ら体得することが、ことのほか重要視される。
茶の湯は、本来は男性の社会性を前面に出した、社交芸術の花とでもいうべき実践の場であるが、一人の自分という人間性を磨き、鍛錬し、表現する真剣勝負の対面の場でもあり、また一服の茶とともに、世俗から離れ、心を通わせるためだけにしつらえた茶室の、独創的な空間を楽しむ、空間体験芸術でもあり、それらのすべてが、もてなしの精神の集大成でもある。
茶の湯の歴史
9世紀の初めに唐より帰朝した最澄が、膨大な典籍とともに、日本に茶の種子をもたらし、その唐の喫茶の習慣を、禅宗寺院で共同飲食儀礼として取り入れ、南北朝の時代には一般化しており、そこから茶の湯が広まり、鎌倉時代の末には一定の茶礼が確立され、室町時代に花開く時代を迎えたという。
時を経て、安土桃山時代、茶の湯に広く傾倒する武将が数多く現れ、その戦勝の褒美は、一国の領地よりも名物の茶器・茶碗が有難がられたという。
明治時代には政財界の大物が、茶の湯の隆盛の後ろ盾となり、立場を超越し、胸襟を開き、心を通わせ、時には政談・密談の場として大いに利用されたという。
戦後は、女性のいわゆる花嫁修業の一つのたしなみとして奨励され、若い女性の間で広まった。
世界に発信された茶の湯
当時の日本の代表的な美術運動家である岡倉天心は、東京美術学校(現在の東京芸術大学)の創設に多大な貢献をした。その岡倉による文明論三部作の内、「東洋の理想」「日本の覚悟」とともに「茶の本」は英語で書かれ、1906年に米国で出版され、大きな反響を呼び、その後ドイツ語、フランス語に翻訳出版されて、ヨーロッパにも広くその茶の湯の精神は世界に発信され、紹介されたのである。ここに茶の湯の精神は、日本の総合伝統芸術としての普遍的な理解と地位を獲得したと言ってもよいのだろう。
利休七則
戦国時代から安土桃山時代に、茶の湯の世界を集大成した千利休は、茶の心ともてなしの極意を次の様な、七つの簡素な表現に凝縮して残している。
- 一、茶は服のよきように
- 二、炭は湯の沸くように
- 三、花は野にあるように
- 四、夏は涼しく冬暖かに
- 五、刻限は早めに
- 六、降らずとも傘の用意
- 七、相客に心せよ
簡単そうで、その実践は至極困難。これができるなら、私はその人の弟子になると利休は言ったといわれる。当たり前、簡単なことが一番難しく、平和への願いという万人の祈りが、なかなか届かない世の中である。