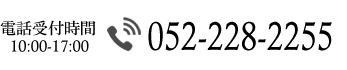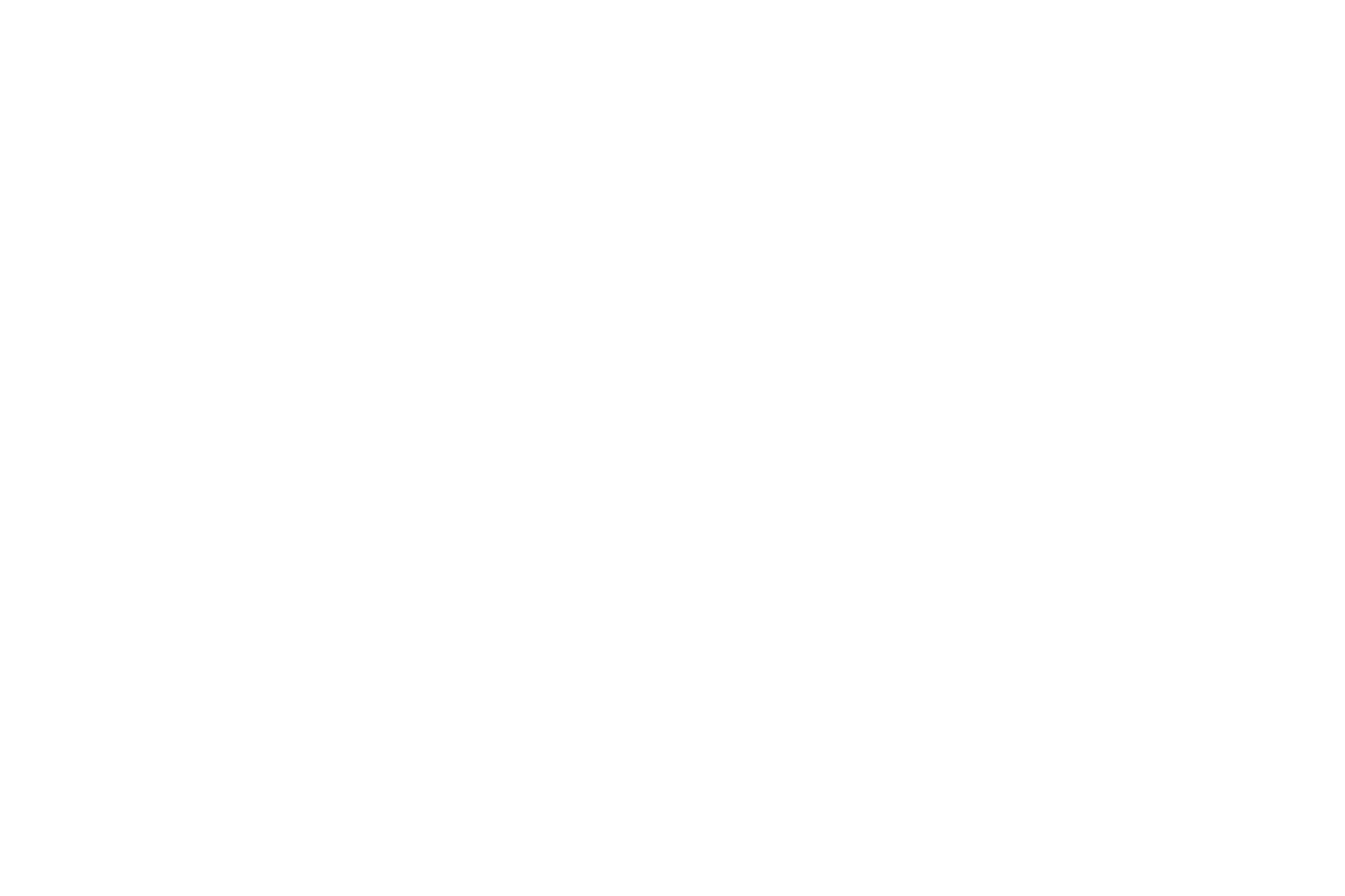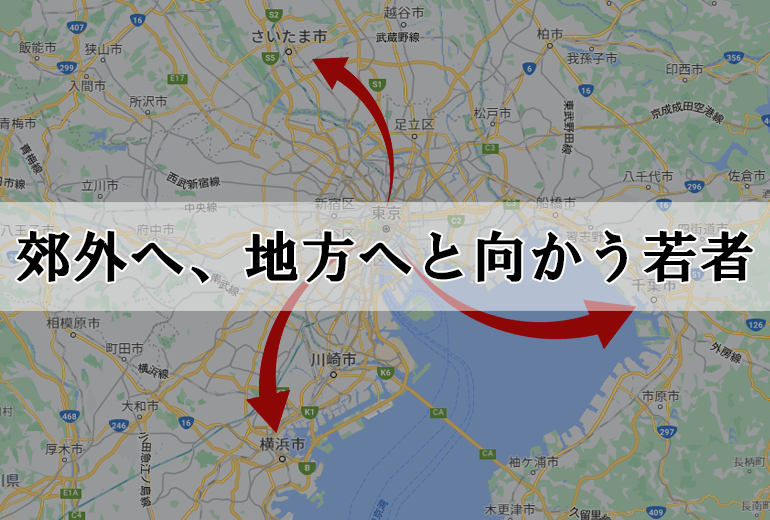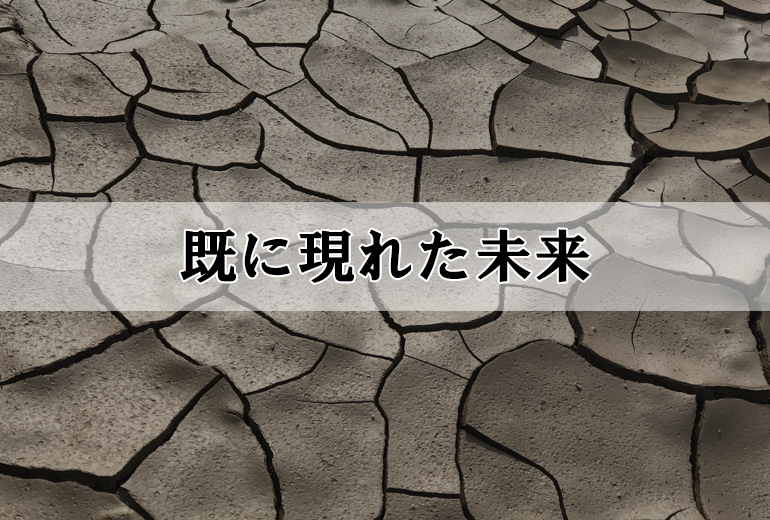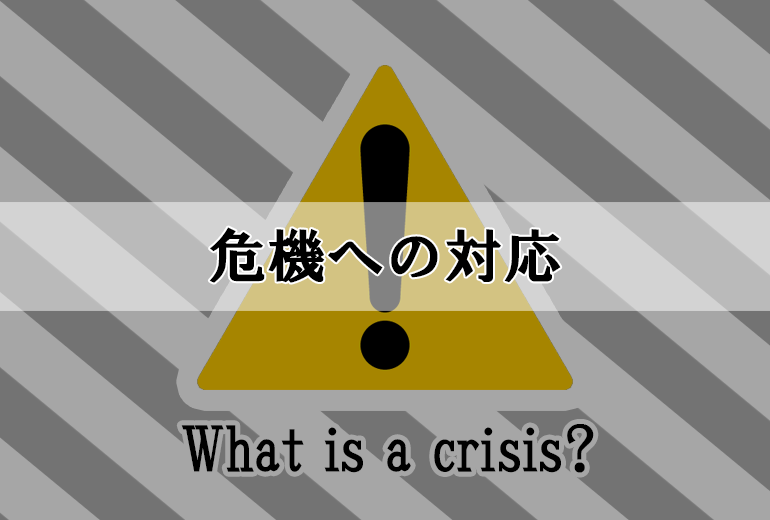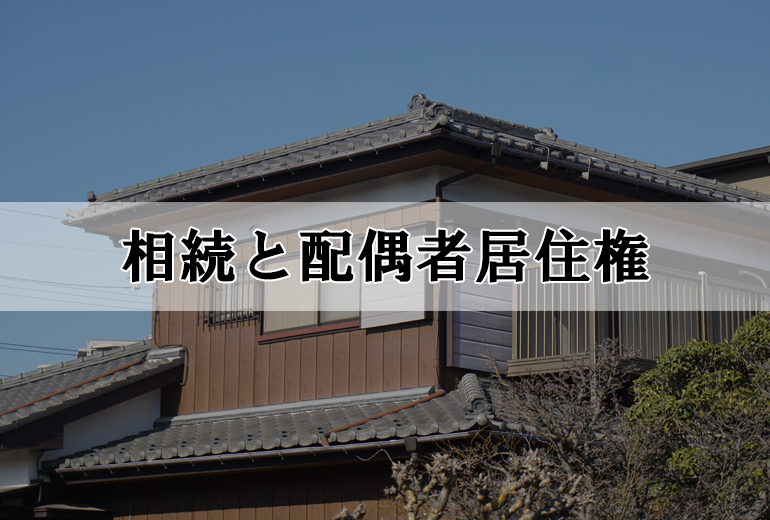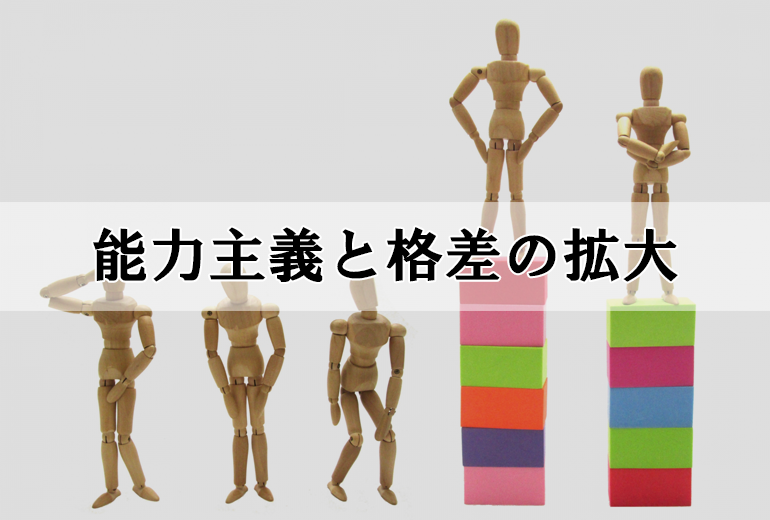老いる貨幣
1929年生まれ(1995年没)のドイツの児童文学作家、ミヒャエル・エンデが表した、『モモ』は子供が読んでも、大人が読んでも面白い。人の話をよく聞く不思議な才能を持つ女の子、モモの周りには、多くの子供と大人が集まり、どこにでもあるものから、新しい遊びの種を見つけ、毎日を楽しく遊んでいた。その平和な村に突如「時間泥棒(灰色の男)」がやってきて、人々から時間を奪っていく。子供も大人もいつしか去ってゆき、自分だけのゆったりとした時間の流れを失っていく。その、時間を巧みに奪っていく「灰色の男」と勇敢に戦い、彼らから時間を取り戻していく物語で、1973年に世に出された。この寓話の中で語られる社会は、まるで現代社会の、大人、子供の姿そのものである。時間の持つ意味と価値を寓話という手法を使いながら、人にとって最も貴重な多くの時間を奪われた現代社会の到来を予言している。現代に生きる大人ほど、切実にその意味を、実感をもって受け止め、語られる言葉の節々にはっとさせられるだろう。
そのエンデは、最後まで人々にに大きな問いを投げかけた。お金の問題である。現代社会は「お金」の病にかかっているという、「ファンタジーとは現実から逃避したり、おとぎの国で空想的な冒険をすることではありません。ファンタジーによって、私たちはまだ見えない、将来起こる物語を眼前に思い浮かべることができるのです。私たちは一種の予言的能力によってこれから起こることを予測しそこから新たな基準を得なければなりません。」とミヒャエル・エンデは言う。