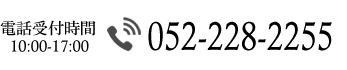マイホーム派か賃貸派か
住宅ローンの光と影
ネットバンキング専業銀行の住宅ローンが好調にその残高を伸ばしている。
最大手の残高は5兆円を超えている。手軽さと低金利が魅力である。
世界中の低金利傾向を敏感に察知し、当分金利は低く留まるとみて、最近では通期で変動金利を選択する人が増えているという。低金利のメリットを十分に受けられることと、いざとなれば固定金利に乗り換える銀行の選択肢も増えている。銀行にとっては一度の取り組みで長く収益確保が見込まれる看板商品であり、審査も定型化され迅速で、返済シミュレーションも瞬時にできる。
しかしマイホームは手に入れた時から、ローンの毎月の返済負担もさることながら、毎日の通勤・通学、移住、転職などの人生のステージ選択に大きな制約を受ける。そのような状況のなか、若者中心に賃貸派が徐々に増加している。
終の棲家
世界を見渡しても人々の移動が活発化し、大移動時代ともいうべき時代となった。
親子数世代に亘り一カ所に住み続けることは非常に稀であり、一生に3度、4度と引っ越すのが当たり前の時代となっている。増してや「人生100年時代」である。ライフスステージがⅠ「幼少期教育期」、Ⅱ「会社勤めの社会生活」、Ⅲ「定年・引退、老後の余生」という三つパターンでは済まなくなった。老後と言うには余りにも長く、生活も年金だけでは心細い。自ら学び、必要な職務スキルを身につけ、第Ⅳ、第Ⅴのステージを自ら切り開いていく必要に迫られる。
その時どこに住居を移すかは、選択肢の重要な前提条件ともなる。住宅ローンを払い終え、住宅費の負担があるかないかは老後の設計においても重大な影響を及ぼす。自宅を処分して都市部のマンションに移住を考える人も増えている。高齢者向け施設も都市部のニーズが高くなっているが、入居時の費用、毎月の費用も高額となる。引越しせずにリフォームして住み続けるか、処分して引っ越すか、老後は誰に面倒を見てもらうのか、人生の最期を果たしてどこで迎えるのか、自宅か、賃貸住宅か、老人施設か、悩ましい問題である。
住宅総数
総務省の統計によれば、世帯数は2015年の5,333万世帯、住宅総数は5,210万戸、その内借家は1,458万戸に増加している。その内空き家は820万戸に増加している(2013年)。
「土地は預貯金や株式などに比べて有利な資産か」という質問に対し、「そう思う」と回答した者の割合は、平成5年度は6割以上だったが、その割合は年々低下しており、平成29年度は30.2%となっている。同時に「そう思わない」と回答した者の割合は年々増加しており、平成29年度は40.5%となっている。日本の住宅需要は戸数だけ見れば充足されており、むしろ増え続ける空き家問題が社会問題化している。
住宅の価値
アメリカなどの欧米と日本では住宅に対する価値観が大きく異なる。アメリカにおけるマイホーム購入は最大の投資であり、その価値を維持・増大するためのリフォームは設備投資であり、よく管理すれば、支払う金利を上回る将来の値上がり益によるキャピタルゲインも十分に期待できる。
逆に日本はどうか。住宅の価値は土地と分離され減価償却の対象であり、税務上の法定耐用年数は木造22年、鉄筋コンクリートは47年である。さらに住宅設備はめざましく機能性が向上し、省エネどころか年間住宅消費エネルギーゼロを目指すZEHハウスなど、耐震性能・耐用年数も向上し、セキュリティ対策も進み、住宅の進化は目覚ましい。2007年に自民党はストック型社会への転換を理念に200年住宅のコンセプトを打ち出しているが、住宅ストックを形成しているアメリカでは住まいの売買に占める中古住宅の割合は83.1%で、日本は14.7%(2013年)である。リフォームに多額の費用を掛けるよりも取り壊し、新築をという選択が未だ圧倒的に多く、住宅の価値は30から40年でほぼなくなり、親の残した古家は壊される運命をたどる。
古代の狩猟採集民と農耕民
21世紀を代表する知性の一人もといえる「ホモ・サピエンス」の著者であるイスラエル人歴史学者ユバル・ノア・ハラリ氏は、「長きに亘り狩猟採集生活を送ってきた人類は、必要最低限の生活道具だけを携え、野原の獲物を追い、木の実・果実を採集する生活は、不安定で、時に生きていくうえで必要な食料にも事欠き、自然の脅威の前に無力で、不自由な生活を強いられていた」という説には与しない。
水辺に住み始め、農作物の栽培・収穫、家畜の飼育により定住生活を始めた農耕民は、より多くの食料を得てより多くの家族を養うようになり、集団生活の中の争い、様々な病気の発生、さらに食料の確保のために多くの時間を割かれるようになり、様々な制約を受け、農耕民は狩猟採集民よりも一般的に困難で満足度の低い生活を余儀なくされたという。狩猟採集民は、飢えや病気の危険が小さかった。必要なその日の食料を確保さえできれば、移動による変化に富んだ生活があり、自由な時間が十分にある狩猟採集民は、興味をひく様々な活動を行い、十分に満ち足りた生活を送っていたのではないかという。
IT・科学技術が驚異的に発展し、その恩恵を受けた現代人は、確かに多くの利便性は手にいれたものの、日々の生活に追われ、ますます自由な時間は少ない。飽くなき「経済成長」を追い求め、資本主義経済が発信する膨大な情報に翻弄され、複雑な社会とその利害関係とそれを取り巻く人間関係に悩む。果たして現代人は、自由に生活の場を移動した狩猟採集民の頃より幸せになったのだろうか。