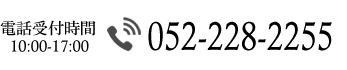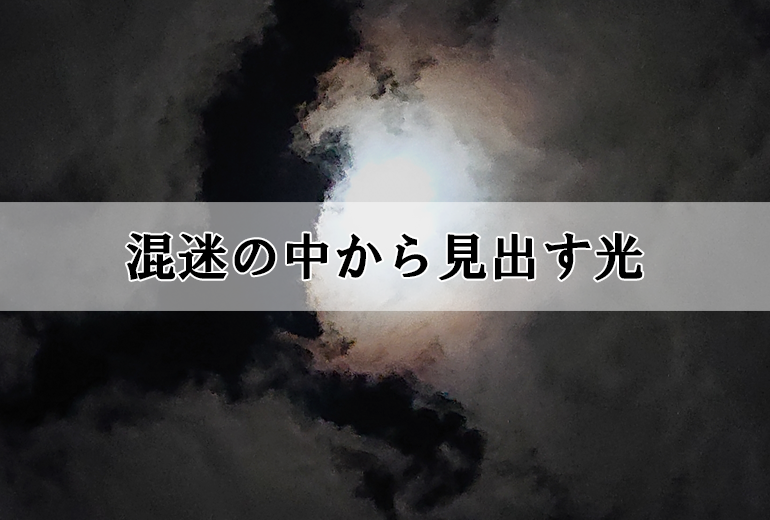混迷の中から見出す光―人類は連続体―
脱中国という欧米の大きな政策転換、フレンドショアリングという同盟国又は同様な価値観に基づき、地政学的なリスクを考慮した西側世界の国際分業体制再構築とでもいうべき、資源・エネルギー・製造工場の再配置を進め、中国への先端技術の移転を何とか食い止めようとしているが、期待するほどには効果を発揮していない。
世界の大きな潮流
しかし一方で、BRICSと呼ばれる国々とアジア・アフリカ諸国は米国と一定の距離を置き、独自の経済圏作りと地域各国通貨の流通比率を高めており、脱西欧とでもいうべき欧米に過度に依存しない域内の貿易と交流を強化しており、徐々に世界は多極化するスピードを速めている。中国をはじめ通貨政策ではドル離れとでもいうべきドル資産の圧縮削減の動きが徐々にではあるが浸透している。米国の双子の巨額の赤字(貿易・財政)に象徴されるような米国一国に過度の負担を強いた世界貿易体制がいよいよ限界に達した表れであり、米国政治はその進路を変え、ついに舵を切り始めた。ドル基軸通貨体制がそう簡単に弱まることはないだろうが、世界でいくつかの貿易体制が並立するブロック経済化が進みそうだ。
米国は自国第一主義を掲げ、貿易関税を主要な取引の交渉手段として利用しつつ、その政策実行に障害となるWHOの撤退、地球温暖化の抑止政策の放棄、軍事防衛費の大幅な削減と見直しを推し進め、貿易・財政赤字の大幅な削減を図るとともに、海外からの国内巨額投資案件の呼び込みと製造業の工場を国内生産への回帰による自国の自動車・半導体・造船などの製造業の復活、金利引き下げによる景気浮揚策、原油価格の低下、医療費の削減、低所得層のへの減税、株価への配慮、不法移民対策の厳格化、伝統的な家族観への回帰など、ここに列挙しただけでも、半年に満たない短期間に驚異的なスピードで今までの米国の政策方針を、すべて大きく方針転換し、過去に見られない勢いで矢継ぎ早に実施しており、戦争終結への交渉も積極的に関与している。
中国は独自路線を進め、「製造2025」で掲げた10の国家的目標は大きな進展をみせており、宇宙開発、ロケット、半導体、造船、再生可能エネルギーなどの主要目標の進展は著しい。しかし、過去の不動産バブル崩壊と金融の不良債権処理は未だ道半ばで、低迷する不動産価格は消費支出の足かせとなっており、預金準備率の引き下げなどの金融緩和・景気浮揚策を実施しているが、米国の貿易関税政策により輸出は打撃を受けており、対抗策とともに、中国を中心とした独自の経済圏作りを視野に各国地域に様々なアプローチを実施している。しかし、日本を凌ぐほどの人口の急速な高齢化進む中で、高齢者の資産は日本ほどには蓄積されていない。
日本は20年以上に及ぶ長期の低成長・デフレ基調から、近年はインフレ経済へと変化し、物価上昇、賃金上昇、人手不足によるIT導入による効率化、生産性上昇、ロボット導入による人手不足解消を進めている。対外的に見れば経済・政治・軍事における米国の重要なパートナーとしてのアジア太平洋地域での地位と重要性は高まっている。逆に言えば米国は日本の政治・経済・軍事費支援なしには、中国の対外影響力の封じ込め政策を効果的に実行できないと見られている。また、半導体分野で技術供与、国際的な投資連携協力に特徴的にみられるように、友好国同士のフレンドショアリング政策によるサプライチェーンの構築、主要製造業分野の国際分業体制の構築で日本に追い風が吹いている。
次の大国インドは、その中立的な外交政策で等距離外交を推し進め、多くの利益と発展を享受しているように見える。世界に多くの留学生を送りだし、世界の先端技術を国内に導入し、自動車などの製造業に力を入れている。さらに海外からの投資を呼び込み、国内のインフラを整備し、国内産業の育成を図り、インドが次の世代で大きな経済発展を遂げるであろうことは世界の衆目の一致するところである。
ヨーロッパは、ロシアとの対立・対峙策が最大の政治的テーマで、エネルギー資源価格の高騰、フランスの原発による電源の確保、レアメタルの確保などの問題を抱えつつ、新たにEUに加盟した北欧諸国を巻き込み、GDP比での大幅な防衛費の増加策の実施を見込んでいる。EUはウクライナ戦争の現実的な脅威を目の前に、米国の抑止力だけに頼れないという認識を深め、ドイツの軍備増強も取り込み、独自の防衛路線の道を歩もうとしているように見受けられる。
日本が多くの人々を受け入れる時代へと変化
インバウンドの急激な増加により、今年は4000万人ちかい外国人が日本を訪れると予想されている。一様に日本の歴史文化への関心は高く、日本の公衆衛生意識の高さ、清潔好きな国民性とともに、礼儀正しさ、社会の安全・安定性が再評価されている。高度な製造技術に裏付けられた製品品質に対する信頼性とともに、日本各地に残る日本固有の歴史・文化・風俗など日本文化全般への関心が高い。様々な理由で日本に移住を希望する人々が世界からやってくる時代は目の前の事実としてある。少子高齢化・人口減少が続く日本には、戦前戦後の困難時期に多くの移民を海外に送り出した過去があり、今度は日本が海外からの労働力確保、介護・福祉・医療の分野への参入を進めることは、持続的な経済成長に不可欠との認識が深まっている。
日本の高度に繁栄した社会に魅力を感じ、仕事を求め、家族を連れて日本に来て働くことを望む海外の人々が増加している。海外から多くの人々を受け入れるのは簡単なことではないが、その覚悟と準備と寛容さが必要とされる時代となったのだ。高齢化が急速に進む現在の日本社会の諸問題と一定の成長戦略両立させるカギは、外国人労働者の受け入れによる経済の活性化にあり、日本に学びたい留学生や、家族ともに働き永住を希望する外国人に、制度的な移住・定住の道をいかに準備するかどうかに懸かっていると思われる。
多様性の受け入れは寛容な社会を形作る
経済発展と歴史的社会的な価値観の形成、現在の経済社会の根本構造に、各地域で歴史的に培われた家族観が大きく影響を及ぼしているとのフランスの著名な人口歴史学者であるエマニュエル・トッド氏の指摘がある。明治以降の日本の西洋社会・文化への対応の歴史を見ても家族観は徐々に変化し、他民族の歴史に培われた固有の家族観に基づく歴史の多様性を認め、文化・宗教の受け入れる余地を認め、互いに共存共栄を図る社会が最終的には多種多様多彩で活力を持つ社会といえるだろう。多くの人々の持つ移民に対する一般的な先入観とは裏腹に、一般論として、移民1世2世が社会に馴染み溶け込もうとする努力は顕著で、その国の全般的な犯罪率よりも統計的に低い数値が出ているという研究もある。基本的な衣食住が確保でき、その国の生活ルールを教え、生活に必要な言葉を学ぶ機会を与えられれば、現状需要を満たしていない労働現場で働き、家庭を築き、税金を納め、その地域経済の発展に寄与するのである。しかし、社会全体で計画的に秩序をもって行われることが強く求められている。
人類の歴史は変化の連続体
周知の通り、大きく見れば人類のDNAの違いはほんのごくわずかであり、人種間の違いはないに等しいとされる。自然人類学の研究で、幅広く人類の辿った歴史をわかりやすく教えてくれる、「ホモサピエンスの15万年」-連続体の人類生態史-(古澤拓郎 著)に依れば、人類はおよそ10~15万年前にアフリカ大陸の外へ進出し、のヨーロッパ・アジア・世界各地に進出し、ついには陸地続きのベーリング海峡を渡り、1万4000年ほど前に北大陸に辿り着き、南アメリカ大陸を縦断し、その南端に辿り着いたのは1万3000年前だという。発展変化の速度は世界の地域ごとに異なり、社会は様々な要素の複合的な組み合わせにより実に多彩な発展の様相を呈しているが、歴史的に見れば、それは切れ目のない連続体(スペクトラム)であると言える。
育った環境、受けた教育、親から引き継いだ資産の多寡、歴史的に育まれた家族制度などに起因する、社会に対する意識の揺れ幅は大きいものの、本質的には時間と場所の違いを乗り越える連続体であるといえるだろう。またこの連続体という概念は、あまりにも世界的な大企業の影響力が国家さえ凌ぐような影響力をもつに至った現代社会において、国家と企業の統治に社会全体が翻弄され続け、個人の存在の意義が埋没していく中で、地域・民族・人種を乗り越えすべての人類が繋がって現在に至っているという「人類はすべて歴史的な連続体」という考え方は、平和共存の世界で互いにその違いと個々の存在を容認し、国々の歴史からの束縛を解き放ち、差別と偏見をなくし平和を推進するうえでヒントとなる言葉である。簡単に言えば、今の置かれた立場は一定不変ではなく、時が移れば立場は逆転し、「お互い様」ということだと理解したい。
世界は相互に深く関連し、良くも悪くも様々な大きな影響を及ぼし合っており、インターネットのニュース・映像を通して、個人の相互の理解・関心は世界的な規模で格段に深まっている。15万年前にアフリカから世界に飛び出した人類は、世界の隅々まで移住し、その容貌の表面的なわずかな違いはあるものの、DNAはほぼ共通しており、話せば分かり合える、理解し合える存在であり、様々な時代、地域の環境に変化に適応した結果、親族の生まれたその場にとどまらず、時と場所を超えて、大きな歴史のうねり流れとして、今後も世界各地に進出し、移民・移住を繰り返していく歴史を歩むのだろう。「人類はすべて歴史的な連続体」としてとらえる著者の言葉は、ますますその有用性を増し、互いの存在と価値観を相互に理解するうえで、大きなヒントとなるだろう。