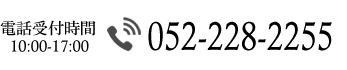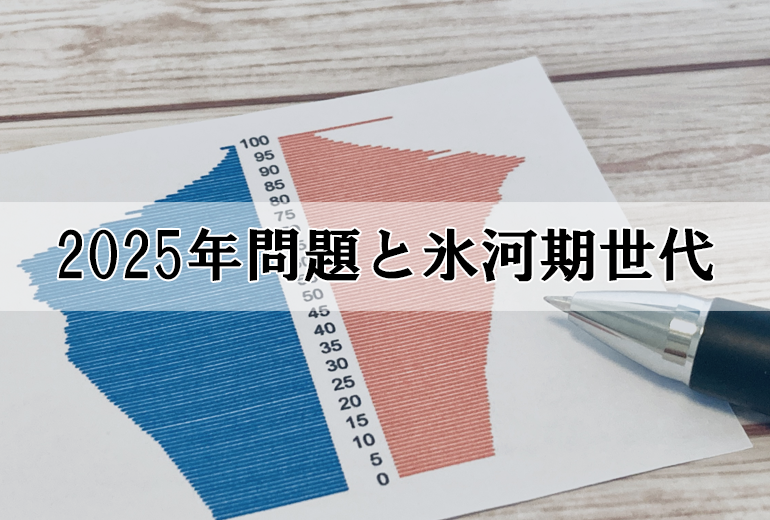2025年問題と氷河期世代
「2025年問題」とは、端的に言えば約800万人の「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者となることで、医療費や社会保障費の増加などの負担は、世代間の不公平感や格差を広げ、今後社会に様々な影響が生じることを指している。一方で、「就職氷河期世代」とは、1990年代半ばから2000年代半ばまでの、不況と経済成⻑の鈍化による影響によって、新卒学⽣が深刻な就職難に直⾯した世代を差し、概ね1993〜2004年が就職氷河期とされている。
就職氷河期の最⼤の原因は、1989年に端を発するバブル崩壊による経済不況と、それによる企業の採⽤抑制である。⾼度成⻑とバブル景気によって右肩上がりの経済成⻑を続けていた⽇本は、平均4%という潜在成⻑率のもと、⼤卒求⼈倍率も最⼤2.86倍(1991年)という⾼い数字を誇っていた。
しかし、バブル崩壊を境に様相は⼀変し、悪化する事業収益を受け、多くの企業は既存社員の解雇を回避する代わりに、新規採⽤を抑制し、1993年には新卒採⽤を⾏わない企業が続出した。その結果、1993〜2004年の⼤卒就職率は平均69.7%まで落ち込み、これは1985〜2019年全体(1993〜2004年を除く)の平均80.1%を⼤きく下回る数字となった。経済危機と社会の劇的な変化、その影響を受けた⼈の数の多さという、全ての要素が同時に重なってしまった結果といえるだろう。
この時期に⾼校や⼤学を卒業し、就職に苦労し、正規社員となれなかった多くの若者は、現在40代50代となっているが、社会経済の中核を担う重要な働き盛りの世代が、低所得、非正規雇用、非婚化による出生率の低下などに大きく影響を与えており、それは今後の日本経済に大きな影響をもたらす大きな社会問題と認識され、国と地方自治体により様々な対応策を講じてはいるものの、氷河期世代の老後の貧困化を招来し、将来の社会不安と社会全体の負担を増加させる要因になるとみられている。
そして、不動産の「2025年問題」とは、65歳以上の高齢者人口が増え続ける中、団塊の世代の75歳以上となる後期高齢化によって、不動産市場にも空き家、相続、不動産価格などにも大きな変化が予測されるというものだ。地方の過疎化と地価下落、都市部の需要集中によるマンション価格の高騰とともに東京圏の一極集中は止まる気配がない。
また、2025年は、米国政治のもたらす影響が世界各地に伝播し、多くの混乱をもたらしている。米国一国主義とも呼ばれるような極端な政治手法は、アメリカに対する今までの各国の信頼感を著しく損ない、内向きで孤立していくアメリカに対し各国・地域は、防衛策・自衛手段を模索し懸命に対応しようとしているが、日本国内では円安効果によるインバウンド観光の増加で観光宿泊関連産業は潤う一方で、人手不足による人件費上昇圧力と、物価上昇による実質賃金の目減り分を補填すべく、今までにない3年連続の高い賃上げ率となり、今年の賃金上昇率は平均5%前後となっている。日本は長く続いたデフレ経済から脱却し、インフレ社会へと様変わりした。世界の大勢は景気浮揚策として金利引き下げ局面であるにもかかわらず、日本経済はインフレ抑止のための金利上昇へと舵を切りつつあるように見える。少子高齢化の一層の進展により社会の活力は衰退していくのか、それともその逆境をバネに新しい変化に対応していけるのかどうか。若者世代の活力を呼び起こすような新しい経済施策を実施し、若者世代を中心とした社会のマインドリセットが求められている。「老兵は去るのみ」であり、世代間の不公平感を煽っても何の解決策も見られない。科学技術における優位性を持つ専門分野をさらに高度化・産業化し、高付加価値経済に移行転換するためにも世代を超えた取り組みが必要とされている。人生は本当に長くなり、80歳を超えて社会経済活動に参加するのは普通になりつつある。誰においても生涯学習とスキルアップが人生の新しい局面を生み出し、個人も社会も経済も成長路線に踏み止まるどうかという、大事な変動期に差し掛かっているのだろう。